【梅雨の養生】「脾(ひ)」を整えて、じめじめに負けない体づくりを
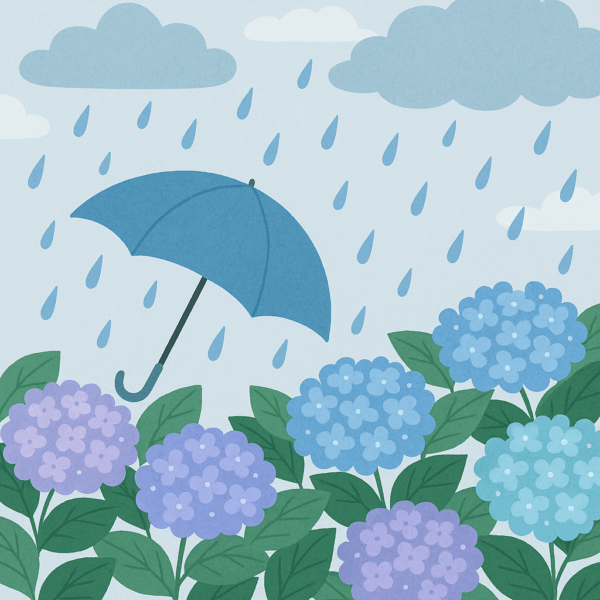
6月中旬、秋田県も平年並みに梅雨入りしましたね。
毎年のこととはいえ、この時期になると「なんだか体が重い」「食欲がない」「朝からすっきりしない」という声がちらほら聞こえてきます。
漢方では、こうした梅雨特有の不調に「湿邪(しつじゃ)」という概念でアプローチします。
中でも重要なのが、“胃腸”に関係する「脾(ひ)」という存在です。
梅雨と「脾」の関係、そしてこの時期を元気に乗り切るための漢方的な生活の工夫をご紹介します。
脾のはたらき
漢方でいう「脾(ひ)」とは、現代医学の「脾臓」とは異なり、
胃腸を中心とした消化吸収の働き全体を意味します。
主な役割は次の3つです。
- 食べたものを消化・吸収し、体に必要な「気(エネルギー)」や「血(栄養)」を作る
- 体内の水分バランスを整える
- 気を全身に巡らせ、体を元気に保つ
このように、脾は私たちの健康を支える「土台」のような存在です。
漢方では「後天の本(こうてんのもと)」とも呼ばれ、生命活動を維持するうえで非常に重要とされています。
脾は湿を嫌う
漢方には「脾は湿を嫌う」という基本的な考えがあります。
湿気は重く、粘り気があるため、脾の消化・吸収・水分代謝のはたらきを妨げやすいとされています。
とくに梅雨時期は、外からの湿気(=外湿)と、体内にたまった余分な水分(=内湿)の影響で、脾が弱りやすくなります。
その結果、以下のような不調が起こりやすくなります。
- 胃もたれ、食欲不振
- 下痢や軟便
- むくみ、体の重だるさ
- 朝から元気が出ない
- 集中力が落ちる、思考がまとまりにくい
これらは、「湿邪」によって脾がうまく働けていないサインといえるでしょう。
梅雨の養生法
1. 食事の工夫
おすすめの食材:
はと麦、小豆、とうもろこし、冬瓜、かぼちゃ、しょうが、ねぎ、しそ など
→ 体の余分な湿をさばき、胃腸を助けるはたらきがあるとされます。
控えたいもの:
冷たい飲み物・生野菜・アイスや甘いお菓子・油っこい食事
→ 脾の働きを妨げ、内湿を増やす原因に。
ポイントは「温かく、消化に良いものをよく噛んで食べる」こと。脾をいたわる基本です。
2. 暮らしの整え方
- 湿気が多い日は、除湿器やエアコンを上手に活用
- 湯船につかって、やさしく汗をかく
- ストレッチや軽い散歩で「気」と「水」の巡りをよくする
- 夜は早めに寝て、胃腸を休める
「湿」を外に出しやすい体づくりには、生活リズムを整えることが大切です。
3. 漢方薬の服用もご検討ください
梅雨の不調が続くときは、漢方薬で体のバランスを整えるのも一つの方法、素早くお体のお悩みを解決できます。
あなたの体質や症状に合わせて、漢方の専門家がご提案いたします。
相談だけでも大丈夫ですし、無料の試飲も出来ます。
梅雨は「脾」にとって試練の季節。
湿気をうまくさばくことができれば、体も心も軽やかに過ごすせます。
ぜひお気軽にご相談ください。