起立性調節障害について
現代医学と漢方医学の視点を比較してみる
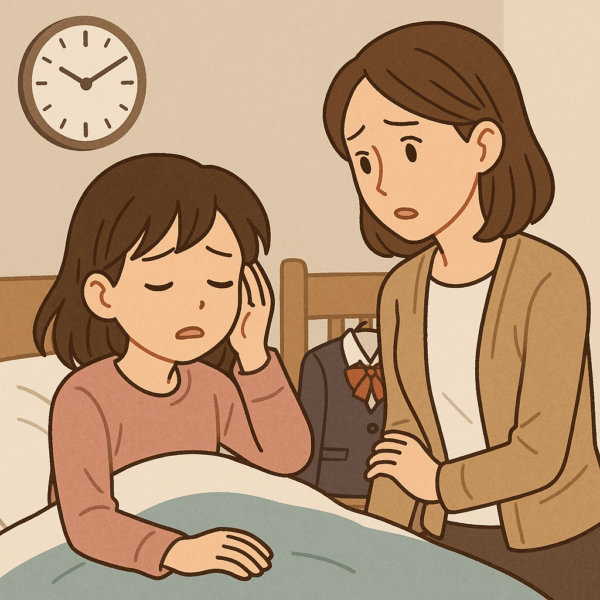
朝起きられない、学校に行けない、いつも疲れている。こうした症状に悩むお子様たちの背景には、「起立性調節障害(OD)」と呼ばれる自律神経の不調があると言われております。思春期のお子様に増えており、当店でもご相談が少なくありません。
心身の両面からのケアが必要とされるこのお悩みについて、現代医学と漢方医学、それぞれの視点と治療の方向性をまとめてみました。
現代医学での考え方と治療
西洋医学で起立性調整障害は、起立時の血圧調整がうまくいかない自律神経のトラブルと考えられています。立ちくらみ、倦怠感、起床困難、動悸、頭痛、食欲不振、吐き気などの症状があり、午前中にに具合が悪く、午後に少し軽くなる傾向があります。
治療の基本は、生活習慣の改善と症状に応じた薬の使用です。
- 水分・塩分の補給
- 睡眠や食事、運動などの生活リズムの整備
- 軽い運動や加圧ストッキングの使用
- 学校環境との調整や配慮
薬物療法では以下のような薬が使用されます。
- ミドドリン塩酸塩、メチル硫酸アメジニウム:血圧を上げる薬(昇圧剤)
- ラメルテオン(ロゼレム):メラトニン受容体作動薬、睡眠リズム調整
- SSRI:不安や抑うつ症状の緩和
漢方医学での考え方と治療の方向性
漢方では、起立性調整障害は「気・血・水」のバランスの乱れ、そして、漢方医学で言う五臓「心」「脾」のアンバランスが原因と考えます。
※ 脾の弱り:消化吸収力の低下、エネルギー不足 → 気虚・血虚
※ 心の弱り:精神の不安定、不眠、動悸に関与
治療の方向性としては以下が挙げられます。
- 補気:朝のだるさ、活力不足を改善
- 補血:めまいや冷え、不眠を整える
- 理気:イライラや不安感、喉のつかえの改善
- 利水・化痰:むくみ、気圧変化による症状の軽減
- 健脾養心:心と脾を同時に補うことで心身を調整
改めて比較してみて、
起立性調節障害は、心と体、そして環境すべてが関わる複雑な病気、現代医学、体質改善に優れた漢方医学など「どちらか」ではなく双方の良いところを取り入れる統合的な重要なのだと確信しました。
相談だけでも結構ですし、ご提案の漢方薬は無料で試飲できます。
お子様たちの健やかな回復を心から願っております。
どうかお気軽にご相談ください。